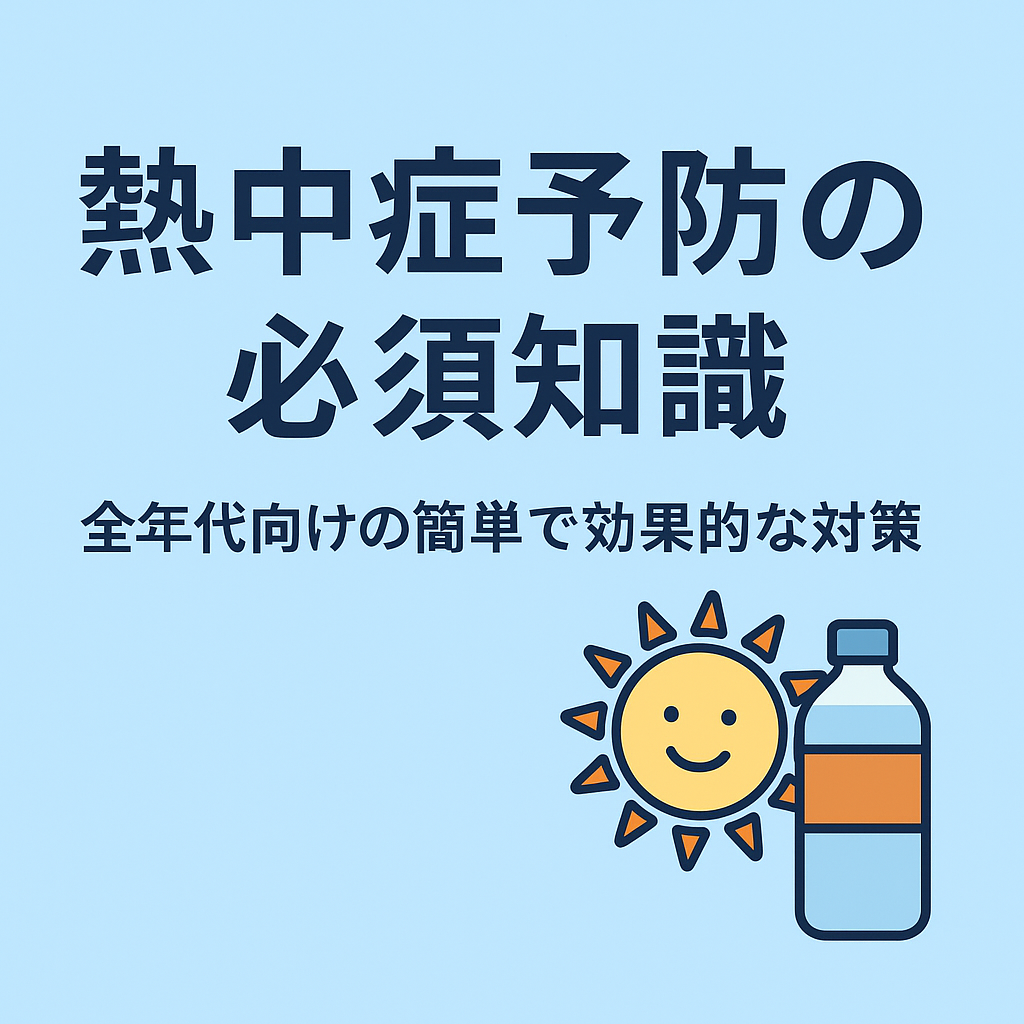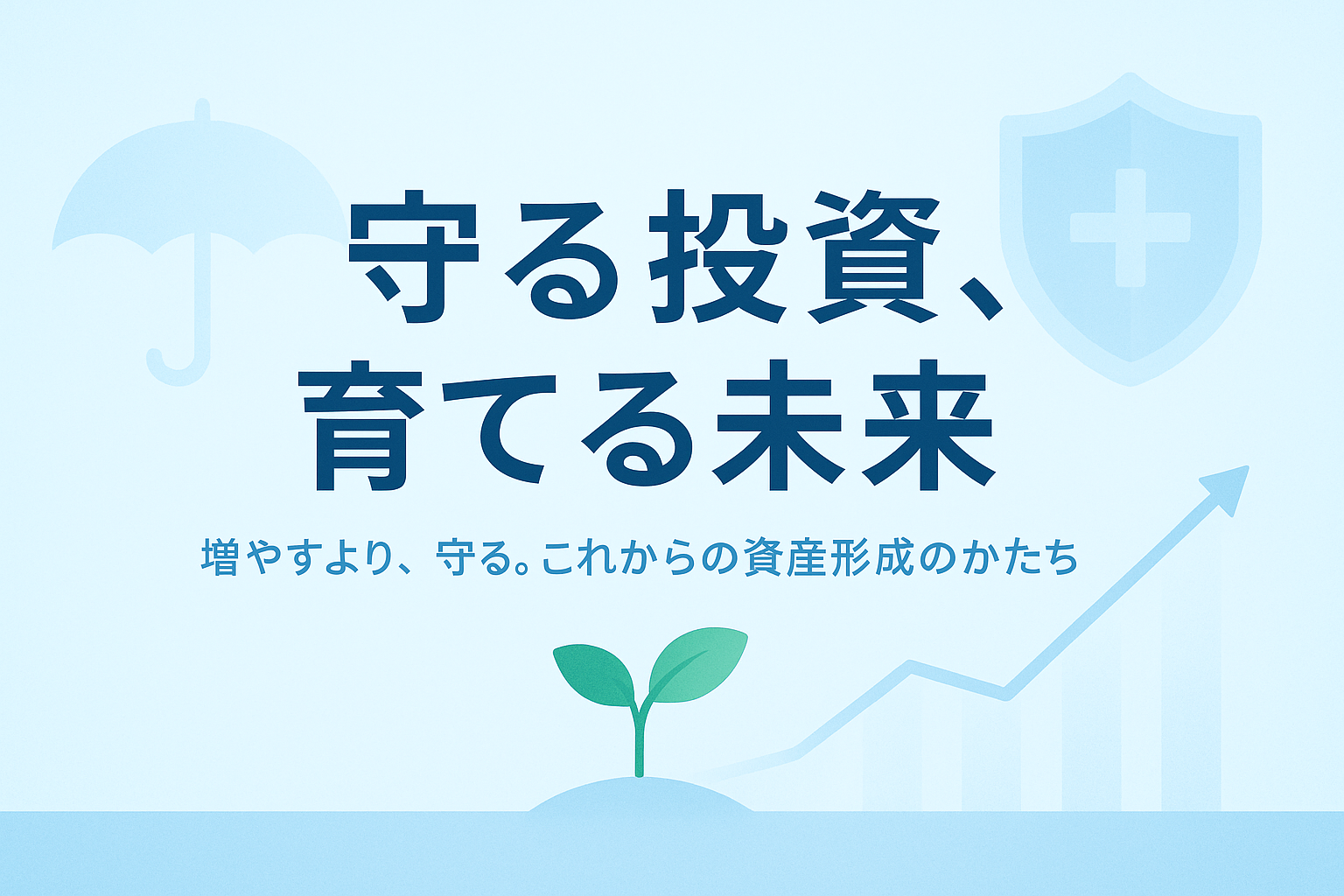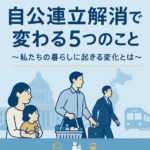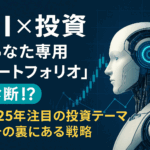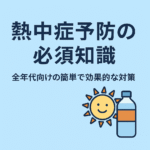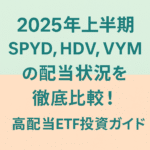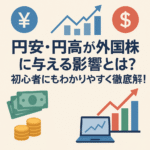「自公連立解消」で変わる5つのこと|家計・子育て・地域への影響をわかりやすく解説
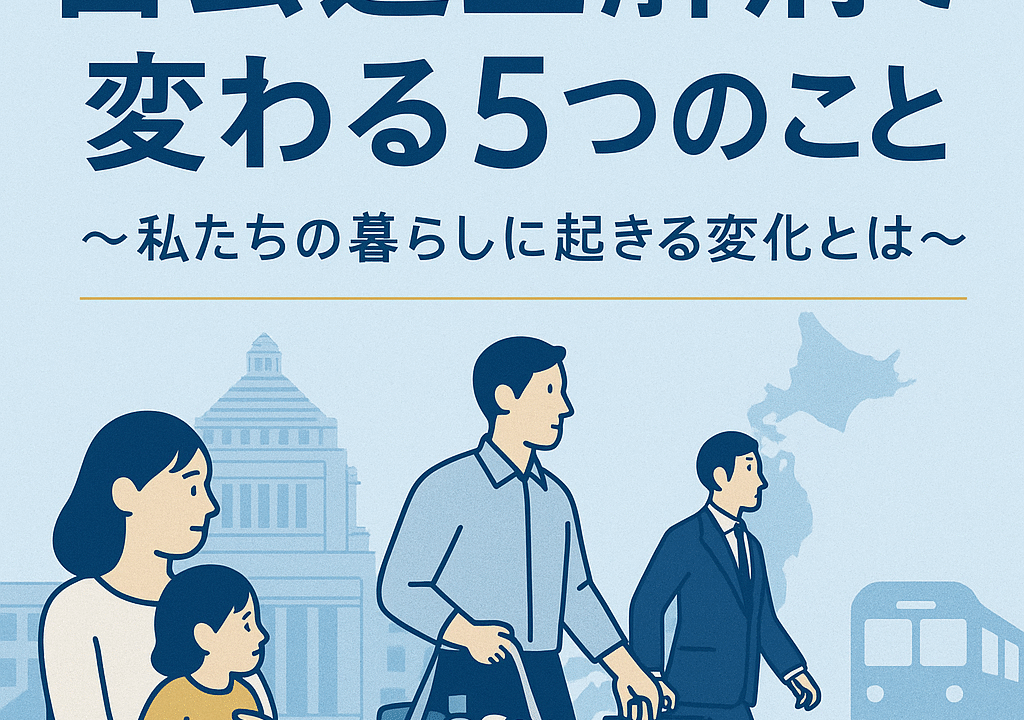
「自公連立解消」で変わる5つのこと|家計・子育て・地域への影響をわかりやすく解説
2025年10月、高市自民党総裁誕生直後、長年続いた「自公連立」が解消となりました。
なんだか難しそうな話に聞こえますが、実はこの動き、私たちの生活にも少しずつ影響してくるかもしれません。
「物価」「子育て」「地域」「税金」――こうした身近なテーマが、政治の方向性と深くつながっているからです。
この記事では、難しい専門用語は使わずに、連立解消の背景と、これからの暮らしにどう関係してくるのかを一緒に見ていきましょう。
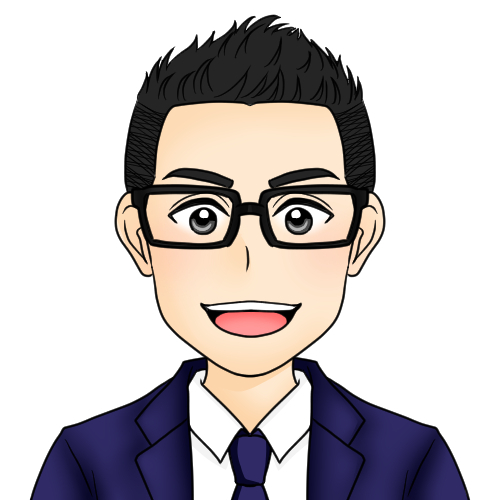
これまでの経緯(ざっくり背景)
自民党と公明党の連立は、1999年10月に当時の小渕恵三第2次改造内閣の下で始まりました。以来20年以上、日本の政治の“安定装置”として機能してきた関係です。
ところが最近になって、政策の優先順位や選挙区での調整、さらに「政治とカネ」の問題などで両党の意見がすれ違う場面が増えてきてました。
そして2025年10月、公明党が「連立をいったん白紙に戻す」と表明。長年続いた関係が大きく揺らぐことになったのです。
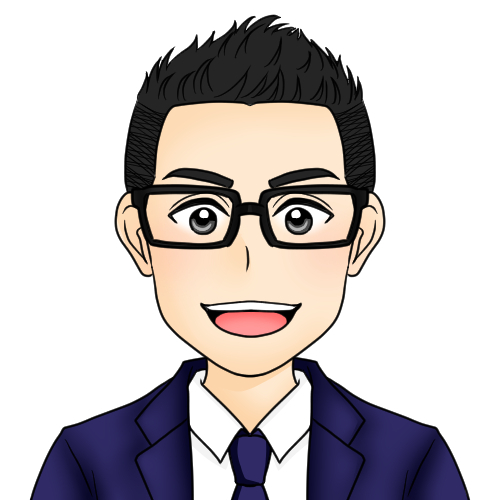
連立解消で何が変わる?(生活への影響)
自公連立の解消が、私達の日々の生活にどのような影響を及す可能性があるのかをみていきましょう☝️
物価と家計の不安定化
連立が解消すると、国会の議論がまとまりにくくなり、補助金や減税策の決定が遅れるおそれがあります。
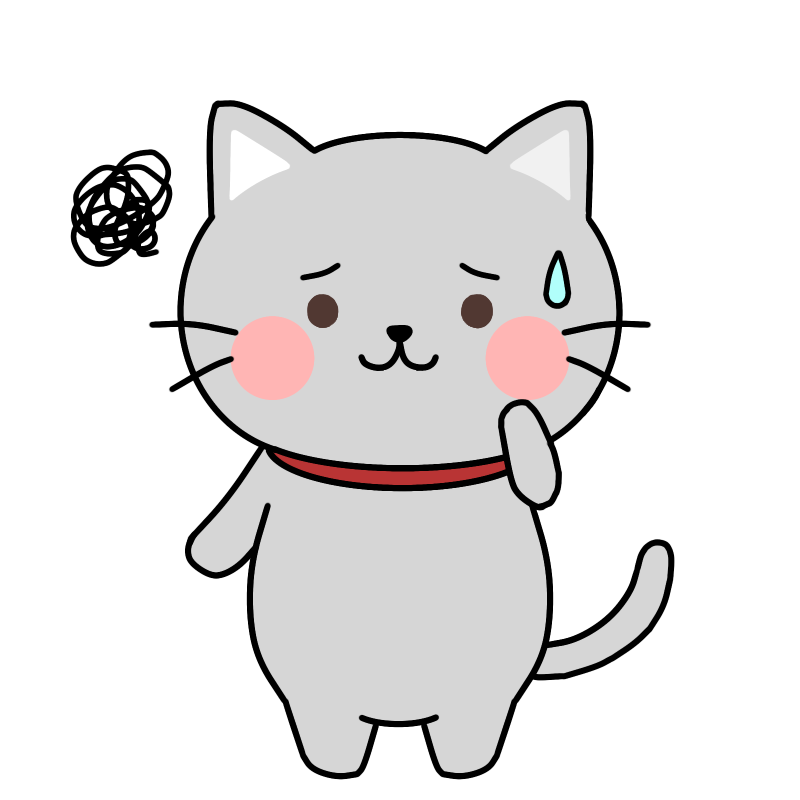
また、政治の不透明さは市場にも影響しやすく、円安や株価変動を通じて物価に波及することも考えられます。
子育て・教育支援の方向性
これまで公明党が力を入れてきたのが、子育てや教育への支援でした。児童手当の拡充、高校授業料の無償化などがその例です。
今後は、こうした政策が見直される、あるいはスピードが鈍る可能性もあります。ただし、他の政党も「少子化対策」を重視しているため、政策競争の中でより手厚くなる可能性もあります。
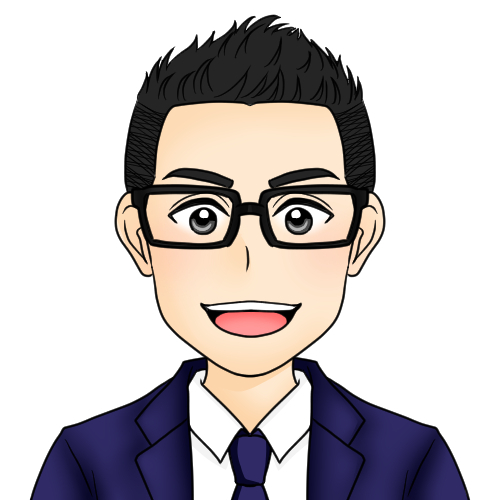
地方と地域経済への波及
地方では長年、自公両党が協力して自治体との関係を築いてきました。そのバランスが崩れると、地方予算や補助金の流れが変わるかもしれません。
観光・インフラ・防災など、地域の暮らしを支える事業への影響も考えられます。
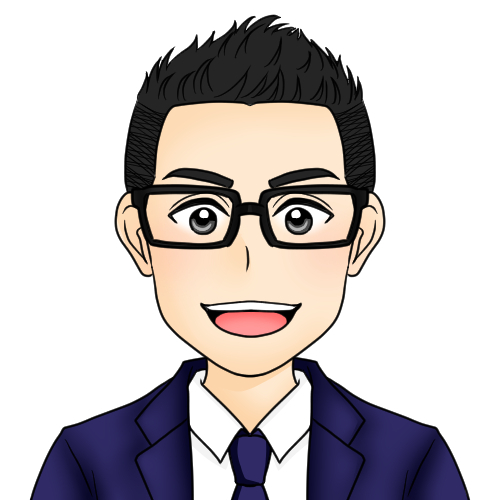
税や社会保障の見直し
政治的な合意が難しくなると、税制改正や社会保障制度の議論も進みにくくなります。「増税か、減税か」「給付を増やすか、負担を減らすか」といったテーマは、私たちの生活に直結する話です。
一方で、各党が“国民目線の改革”を打ち出そうと競い合う動きも期待できます。
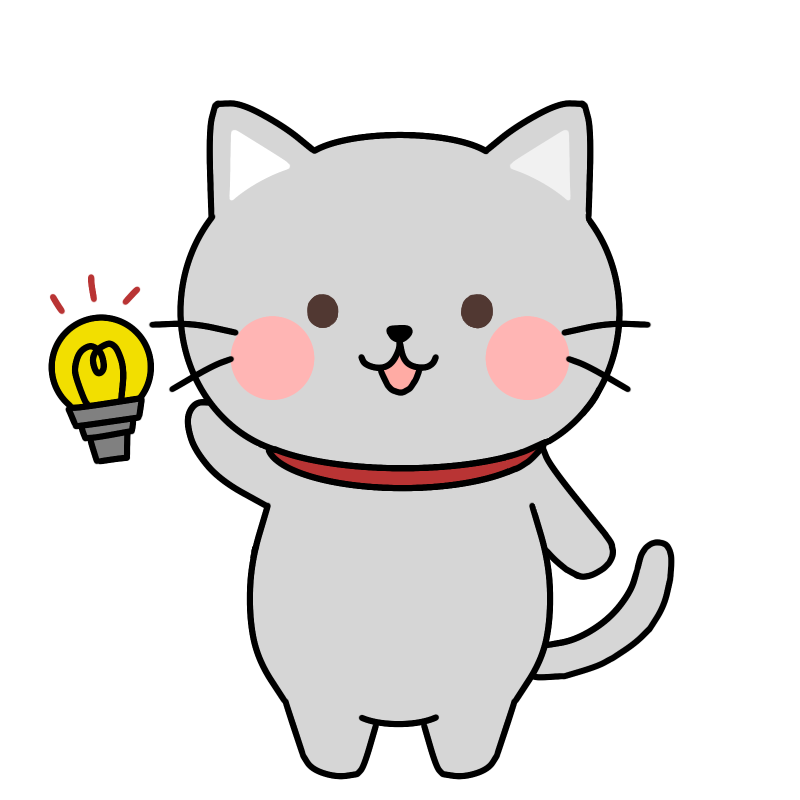
雇用・働き方への影響
連立が解消し、政治の方向性が一時的に揺らぐと、企業はどうしても先行きに慎重になります。
新しい投資や採用を見送る動きが出れば、雇用環境や賃金上昇の流れに影響が出るかもしれません。
また、政府が進めてきた「賃上げ支援」「中小企業補助」「働き方改革」などの施策は、国会での合意が必要なものが多く、政治の停滞が続くと制度の見直しや実施時期の遅れも考えられます。
一方で、政党間で「働く人を支える政策」を競い合う形になれば、リスキリング支援やテレワーク環境の整備、非正規雇用の待遇改善といった分野が強化される可能性もあります。
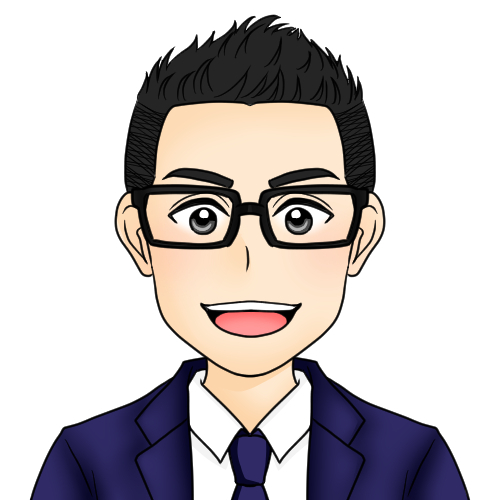
これからどう動く?(展望とわたしたちの役割)
最後に、今後の展望と私達が意識すべきことについてお伝えしてまいります。
政党の再編と新しい関係づくり
連立解消によって、政党間の組み合わせや協力関係が変わる可能性があります。
公明党が野党側と距離を縮めるのか、それとも中立的な立場で政策ごとに協力するのか。また、自民党がどの野党と連携を模索するのか。この再編の動きが、次の選挙や政策の方向性を左右していくでしょう。
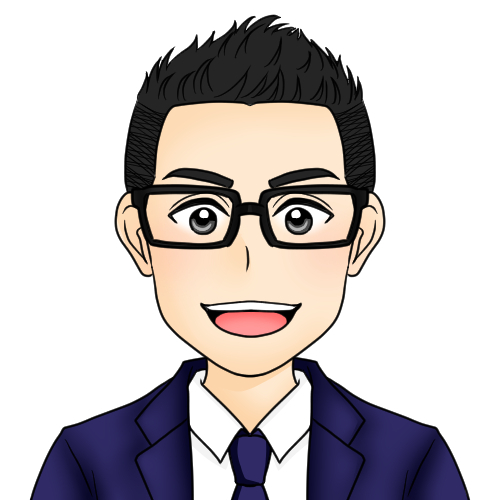
「政治に関心を持つ」という一歩
政治は遠い世界の話ではなく、毎日の暮らしの延長線上にあります。補助金、税金、子育て支援、医療費――どれも政治が決める仕組みの中で動いています。
だからこそ、いま大切なのは「自分の暮らしに関わる政治を知る」ことです。ニュースの見出しを一歩踏み込んで読む、候補者の政策を比べてみる、それだけでも立派な“政治参加”です。
政治の方向は、私たち一人ひとりの関心によって決まっていきます。例え一人ひとりの影響はごく僅かだとしても「国民の総意」として結集すれば、政治を動かす大きな力となり得ます💪
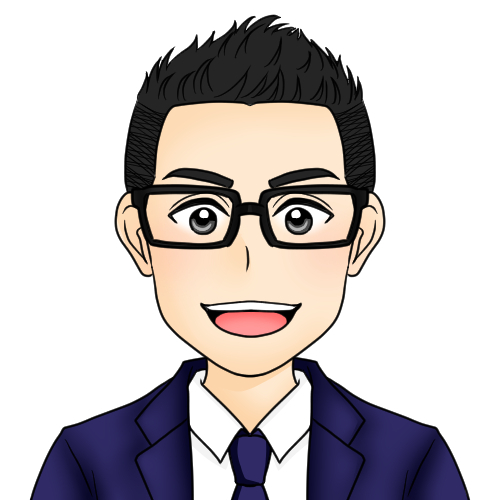
🗳️ この記事を読んだあなたへ: 政治を知ることは、暮らしを守る第一歩です。まずは自分の生活を通じて、政治に関心を持つことから始めてみてはいかがでしょうか?
では、SeeYou❢